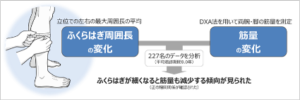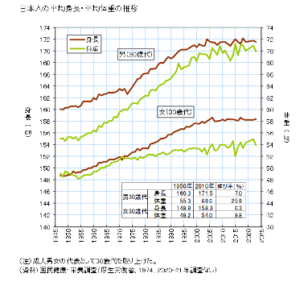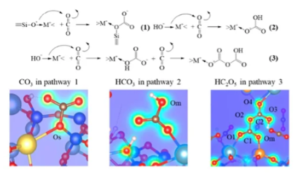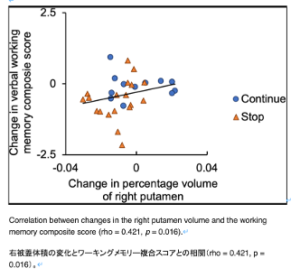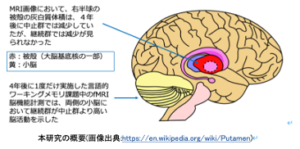EUの自動車を巡る新ルールはEUに輸出する自動車メーカーおよびバックアップの研究機関にとって非常に多忙な夏を送っている。EUは次世代環境に良いエンジンはディーゼルだとしたものの、排気ガスデータが嘘と米国から指摘された。そこでCO2排出ゼロの電気自動車なら文句は言わせないとして、ガソリン車(ハイブリッドを含む)を1930~35年には廃止すると宣言し、BEV車を製造し補助金付きで市場に流した。
やがてEU各国の資金が底をつきそうになると補助金廃止。そこに安価な中国製BEVが登場するとあっという間に市場を席巻。補助金がなくても購入できる車体価格。欧州自動車メーカは二つの対策を出してきた。ここでは非関税障壁を取り上げる
・関税 対中国 従来の10%を最大45%に(対日本は現在10% 7年かけ0%、対EU,米国への関税0)
・EUのグリーン・ディール政策(イコール非関税障壁)

これらの影響を大きく受けるのは日本、中国。そしてEU国民。日本・中国はわかるが、なぜ理想的な環境を作るための規制がEU国民を苦しめるのか? それはとどのつまり、これらの諸政策が実現した時の車両価格を想像するだけで納得できるだろう。
BEV新車価格及び電気料金維持費で家庭の可処分所得をオーバーしており、さらにリサイクル費用・クルマ設計・新ライン償却費 が価格に転嫁される。長期にそれまでのエンジン車やハイブリッド車を保持していると「リサイクル社会に適さない人だ」と言われかねない。やがてEU域内の自動車工場停止、社員リストラ 社会貧困化につながる懸念もある。
米国車はEU市場では販売量がごく僅かなので対策は何もしない。それどころか米国トランプ大統領はCAFÉ(自動車メーカーの平均燃費を規制する制度)GHG(温室効果ガス)規制の今後の計画は見直し(廃止の方向)で動いている。BEVのカーボンクレジットで巨大な利益を獲得したテスラは今後クルマを製造するより、溜め込んだ100兆円を自動運転などのソフトに注ぎ込む模様。
クルマメーカーは種々の規制を設けられてもパスできる技術・資金・経営方針を十分活かしてクリヤーできるか、それともクルマ製造をやめソフト開発企業に転身するかのどちらかに絞られるであろう。 もっともEU国民は冬場のBEVに閉口し、日本勢のハイブリッド車の販売量が増加。さらに日本の軽自動車が紹介されると、これだ!と一種のブームとなっている。
クルマに限らず、理想実現には衣食住(+医職)を満足してからの話だろうと思う。 地球温暖化は確かにある。中国、日本、インド諸国は猛暑に襲われている、但し欧州は逆に冷夏。温暖化の原因は単なるCO2のみではないが、無理やり自国の都合に良いようにルール変更するのはアングロサクソンの特徴といえば言い過ぎだろうか。