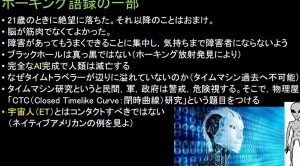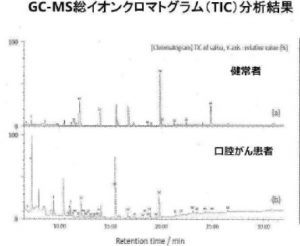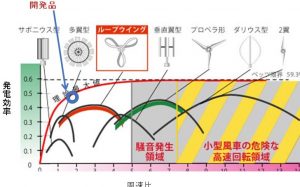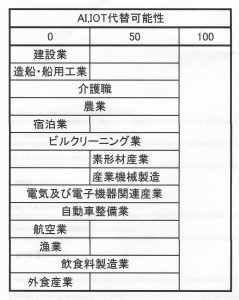ある大学の卒業生で会社や大学を定年後も活動している勉強会がある。大学が違う小生が招集されたのは訳があるが、いつも皆さんの活発な活動に圧倒される。3ヶ月に1回の頻度で開催されている。持ち回りで研究発表をする。2時間を超える講演もあり、活発な質疑応答が繰り広げられる。議論が熱くなると英国テイストのティータイムとなり、後半のもう一つ発表を聴く。半導体の過去と将来をわかり易く、かつ次世代デバイスを解説し展望する人。国家戦略上負けることができないコンピューター特許係争を凌いだこと。工学部出身ではあるが芸術ディレクターとして活動している人は日本と欧州の芸術文化の違いを解説。つい最近はホーキング理論について。タイムカプセルの理論解析など学生時代をいい加減に過ごしてきた身としては、難解な理論をさらりと説明する人の粋で余裕のある姿勢は輝いて見える。なかなか高いレベル。
覚悟はしていたが、ついに小生の番となった。そこで、進展が速い「3Dプリンターのよもやま話」のタイトルで基礎からメディカルへの応用などを発表。コスモサイン加藤社長と共著の歯科技工紙連載2018年1月号~5月号)からもネタを利用した。進展が速い分野だけに、次の講演を依頼されてしまった。3Dプリンターが製造世界をどのように変えるのかに皆様の関心がある。
会社の現役を退いた人もいるが微塵もそんな雰囲気はない。講演・発表のあとは恒例の飲み会。質疑の続きや、近況報告など実に明るい。ほとんどは会社経営層や大学教授職を退いているが、起業や別の機関で現役を続行しておられる。何かの仕事をしていることが元気の素なのか、元気だから仕事ができるのか?多分前者であろう。
ある会社の懇親会で「キョウイク」が話題に。「教育」ではなさそうな話の流れ、やがてこれが「今日行くところある?」の略だと判明。定年で自由の身になったものの、やるべきことも無く、行くところも無く。行くところを考えるのもシンドイの話の流れ、やれやれ。アクティブシニア層と大変な好対照だ。女性なら「キョウモイク」でしょう。
幼児教育の型、お受験の型で小中学校を選択し、それなりの高等教育の型を経て、有名な会社に入り、会社の型の中で活躍する。しかしながら、定年後は「型がない」。さて、どうしたものか? 手許には会社時代の名刺だけで、もはや関係が薄いどころか顔を出せば迷惑顔をされる。第一男のプライドが許さない。大雑把に言えば、こんなところだろう。
昨今、副業を認める会社が出つつある。同じ業種ではなく異なる世界にタッチすることで視野が広がることを期待してのことだろう。そして定年後にも活躍できるようにと。至れり尽くせりの制度?それとも給与対策なのか。ひねくれないで前者だとして足を一歩踏み出すのも有益ではなかろうか。
尚、この大学は面白い経緯があって設立されている。江戸時代の各藩では特有の陶磁器があり技術を他に漏洩すると処罰の対象であった。鍋島、伊万里、古九谷、清水などは独自の技術と商圏を確保していた。それが新政府になったとき、各藩の技術を解放し集大成すべく愛知の瀬戸・多治見にセラミックセンターを設置、大学を東京は蔵前に設置した。
なので流派が多少違う小生でも受け入れる素地があったのだろう。陶磁器は主要産品として輸出を請け負った。蔵前は東工大となって有意な人材を世に送りだしている。東急の大岡山が手狭になって長津田すずかけ台に広大なキャンパスと最新鋭の設備がある。大学開放の時に訪れるのも良い。技術の融合が根源にあるのか、工学と医学の境界を融合させて新境地を開く諸先生方がおられる。
話は飛ぶが京都・清水焼では最先端のセルロースナノファイバー利用で新境地を拓こうとしている。その京都は陶磁器技術の統合・発展に貢献している。淀川から清水坂まで燃料運搬の拠点が松風発祥の地でもあり歯科とは無縁ではない。
おまけ 冒頭のホーキング勉強会資料より抜粋。 完全なAIで人類滅亡と予言。厳しい時代になりそうだ。