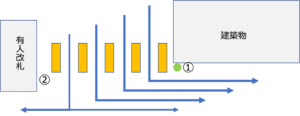コーヒーは毎日飲む。平均3.5杯/日。ケーキがあれば紅茶。和菓子があれば緑茶もいただく典型的な日本人。近年では日本人はお茶よりコーヒーが常態化しているが、本当のところコーヒーが美味しいと思って飲んでいるのか分からない。自分がそうだから。
豆の産地・種類、焙煎程度、粉砕機、フィルター、お湯温度、注ぐパターン、速度などにこだわってみての試行錯誤がいつまでも続いても解にたどり着いてはいない。実験計画法の手順により最適解を求める工学的アプローチは馴染まない。その年の天候により生豆の生育状態が変わるなど変動要因がある。近くの地区センターの広報にコーヒーの淹れ方教室のお知らせがあったので応募した。抽選に外れたが、なんと競争率は100倍。平日の開催なので応募する人も時間に余裕がある人々。逆に言えば試行錯誤をしている人々がなんと多いこことか。
抽選に漏れたこともありネット動画をあれこれチェックしたが、個人の立場や器具メーカーとして動画がアップされている。個人の趣向や器具メーカーの思惑が混在しているのはあるが、結局、味については“美味い、酸味、苦味”の超個人的定性的感想しかない。動画の批判ではないが、伝えることの難しさが極端に表れていることの例として取り上げたに過ぎない。
コロナ禍が日本を襲った初期のころ、リモートワークにコミュニケーションは頼らざるを得なかった。知人とコロナ明けはどうなるかについて話をしたことがある。両者の意見は『もとに戻る』だった。だが世間ではソロキャンプでも仕事はできる、移住先でも仕事はできるとして、もて囃されたのはご承知の通り。従来通りの仕事はインフラ基幹関係や医療従事などに絞られていた。量販家電では、時折立ち上がって作業をするための上下する机や長時間のデスクワークでも疲れないe-sport用の椅子、カメラ、ヘッドセットが大きな売り場を閉めていた。
つい最近、twitter社を買収したイーロンマスクは週40時間通勤してワークすることを命令したとニュースになった。週40時間とはなんと短いとは思うが、出勤命令に従わない場合は即クビには流石に驚いた。筆者は知人と「やっぱりね」と。
欧米のオフィスは大部屋でなく、個人ごとに区切られた空間にいて、一種のリモートワークのような作業形態ではあるが情報を共有伝達する仕組みはある。日本のそれは大部屋方式(最近では個人の机がなく島が点在する共通机方式)になっており、雑談も含め情報の伝達は優れていた。昔は内外との伝達手段は電話であり、他人の仕事も自然に把握することができた。今は静かにパソコンタッチをするだけで極端には隣の人にもメールをする始末。(電話ができない人が増加の背景もある)また、メールなら途中で修正できるが、電話だと口に出した瞬間から後戻りは大変だが、その人の味であり考え方を理解するに有用なのだ。
日本の「和の強さ」は時として弱者の戦術と揶揄する風潮なきにしもあらずの最近だが、先日の対ドイツ戦のサッカーは適材適所、臨機応変、変幻自在の戦術が結果論としてハマった。しかし、ベンチ、スタッフの「和の一体感」無くして、なり得なかったのは誰しも感じたはずだ。
リモートワークに適している職種と人材がいることも事実であるが、job to do が明確になっている場合に限られる。日本のサラリーマンでは5〜10%程度ではないかと推定している。普通は上司の仕事の仕方などを参考に自分の業務以外に自分なら何ができるか考えながら成長するのが普通なのだ。長期的戦略を企画する場合においては社内の垂直・水平および社外との切れ目のないコミュニケーションが必要となる。時々に会うだけでは「絵そら事」「お遊び」として受け取られ、いつまでも実現しない。そのうちストレスが溜まる状態になる。
冗談半分で言えば、大阪のおばちゃん井戸端会議的な伝達方式がよほど適している。展示会では若いイケメンが説明員として立っていることが多い。ところが、肝心のところに客を誘導する前段階の会話が念なことが多い。遠いところから時間と費用を使って視察に来た人に「あう価値、会社を気に留めてくれる」を醸し出すことが求められる。そのためには顔のシワにそれらを染み込ませたシニアや気さくな女性の方が効果ある。展示品だけで釣り上げることも、展示品を餌に大鯛を釣ることも展示会では求められるが、それが可能なのは、言語的にブツン・ブツンと切れがちで繋ぎが少ない標準語よりは、繋ぎに繋いで最後はほっこりするように落とし込む関西的言語が好ましいのではないか。もちろん偏った見方ではあるが、首都圏出身者でありながら、赴任経験などでそのポイントを把握している人もいる。その意味でDXを営業に持ちこむことの限界はある。単なる注文とりで営業マンと呼ばれても良いのなら別だが、それでは人間をしているには勿体無い。そうは思いませんか?