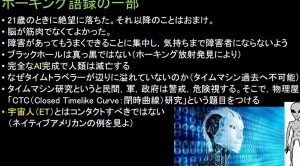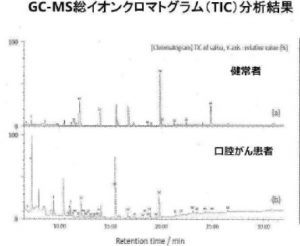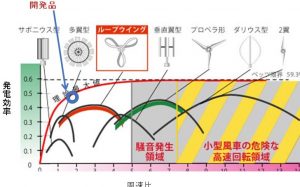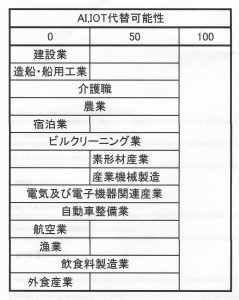<はじめに>
米国は国内シェールガスの生産量が増加したことで、①中東からの原油輸入に頼る地政学から距離を置き始めた②シェールガスの価格に引っ張られ原油価格はOPECが以前よりコントロール出来なくなってきた ③プラスチック原料としてシェールガスが利用され、大規模なエチレン、誘導体生産プラントの能増、新プラント建設が米国に軒並進展している。このところ強気の米国であるが、根本的に自前でエネルギー確保も原因の一つである。シェールガスについては2017.12.06のブログで触れたので参照して下さい。-182x300.jpg)
今回は海ゴミ問題でプラスチックスが敬遠され新規大型プラントなどありえないとのイメージがある日本からみて、米国の事情を眺めた。
参考)2019/1/14付日本経済新聞
<3R意識>
日本ではレジ袋有料化やエコバッグ持参が進んでいる。海ゴミ問題でプラスチックへの潜在意識の流れが変わりつつある。如何にもプラスチックスは環境に悪いとのイメージが消費者の潜在意識があるようだ。このテーマについては、このブログでも取り上げたが、プラスチックはトータルのエネルギー消費、炭酸ガス発生量で計算されるLCA(ライフ・サイクル・アセスメント)では決して環境に悪い材料ではない。但し、より良い方向としては、3R(Reuse,Recyle,Reduce)を従来よりを進めることが重要であることは言うまでもない。
環境立国先進国を自負していた欧州の国は現実はゴミを中国に輸出して、自分の目の前はクリーンだと主張していたが、中国から拒絶されると頭を抱えている状態。フィリッピンでも某国に返品する動きもあるなか、日本のリサイクル商品は消費者の分別意識、業者の徹底した選別と洗浄など工程が優れクリーンだけに中国のプラスチック加工業者からの引き合いが非常に強い。プレスチックスペレット(粒)製造のコンパウンダー業界の稼働率が100%を越えている。日本以外の国とは対象的である。日本は環境先進国などと空威張りはしないが、着実に実行している。国際スポーツ大会で敗けても観戦後に掃除をしてゴミ持ち帰る若者は世界に衝撃を与えた。環境とマナー意識の高い国柄であるとの認識が海外に浸透してきた。嬉しいことである。
<米国プラスチックスプラント能力増強>
さて、日本でのプラスチックス製造能力はここ20年は横ばいである。中国、台湾、タイ、インドでの製造能力拡大が著しいのはご存じの通り。一方、米国についてはシェールガスを生産をしているから、安価なプラスチックスを製造するのだろうと漠然と思っていたところではないかと。
その漠然イメージがクリヤーになってきた。北米でのエチレン生産や誘導体のレジ袋メイン材料の高密度ポリエチレン(HDPE)の製造能力拡張・新設計画が目白押しである。
2013~2015年までにガルフ地区でのHDPEの能力増強分90万トン/年は稼働済みであり、2017年から2021年までに能力増強するのは295万トン/年と驚異的に伸びを予定している。2025年までに更に150万トン増強と、留まるところはない。この背景にはシェールガスが関係していることは言うまでもない。
米国は従来は中東からの原油を輸入してクラッカーにてエチレンなど誘導体を製造する一方で天然ガスからのエチレンを利用してのHDPEや低密度ポリエチレン(LLDPE)を生産していたが、シェールガスの生産量が増加するにつれて、中東からの原油輸入は減少し、むしろシェールガスを輸出するとの立場は変わってきた。
それでは米国は日本の製品構成群と似たようなプラスチックス用途に向けるのだろうか疑問が出てくる。
<新増設プラントのプラスチック用途>
先のHDPE(日本ではショッピングバッグ・薄肉高強度フィルムがメイン)だが米国のそれは中空製品とパイプで圧倒的パイプ用途とのこと。鋳鉄管では錆問題と地震に弱い。継ぎ目からの漏水があるなど欠点はあったが、大口径では樹脂では出来ないものもあり、依然鋳鉄管が利用されている。大口径パイプには機械設備投資が必要であり、かつ樹脂への信頼確認が不十分であることから見送られてきたことは事実ある。信頼性試験については北海道での埋設試験が漸く2年目で、日本ではまだまだ先ではあるが、ISO規格制定の作業はおそらく今年中には終わると勝手ながら予想している。
そうなると、パイプは大型需要となること、海ゴミ問題とは無縁であることが一層進むことが予想される。
かって塩ビはダイオキシン問題やなんだかんだと非難され目の前から消えたが、パイプは国内より米国の活発な需要に支えられ信越化学の収益率は化学メーカーの中でいつもトップの位置を占めている。
これのHDPEポリエチレンバージョン。でも哀しいかな日本の石化メーカーでシェールオイルに対抗するようなコスト構成、製造規模から競争力は低い。
パイプ加工メーカーもトップ3強を除けば、弱小で大型パイプを供給する能力がない。各家庭へ供給する細い水道パイプの製造設備はあるものの、大型パイプ製造は試作段階にある。一方、鋳鉄に限らず鉄は安価である。なので、安価な製品を価格の高い(原料及び大型投資見合いでの加工費用)プラスチックパイプで置き換えことは、疲弊している地方自治体からみると、即置き換え実行とは行かない事情がある。
プラスチックパイプは①錆ない ②漏水がない ③地震など地盤が変形しても伸びて破断することはない ④極端にいえばトラックの荷台にパイプ成形機を設置して加工しながら現場で敷設することが可能 ④製品寿命は電力ケーブルなどと同じ添加剤配合をすれば100年は持つ設計が可能 とメリットは大きい。
事故、地震などで給水できないと水のありがたさが分かるが、長期的な経済性を理解して手を打つのも予算の使い方だと思う。